アケボノツツジに魅せられて
五葉岳 1569m お姫山 1550m 乙女山1517m
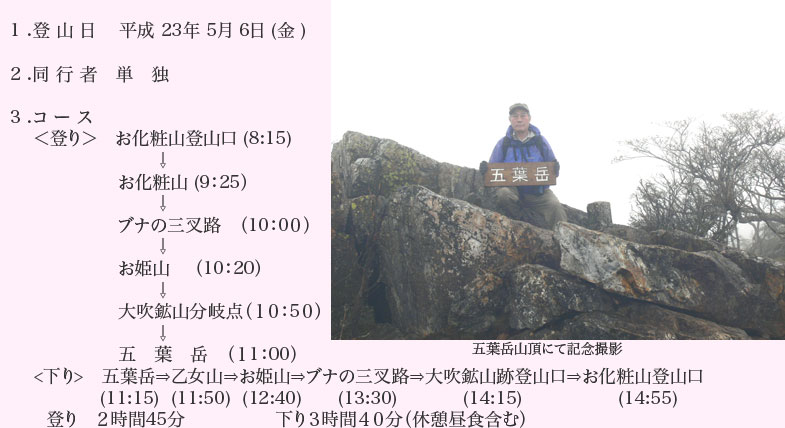
五月の連休あたりの大崩山地は、どの山もミツバツツジとアケボノツツジで例年華やいている。今年もその時期が来た。今年は気温が低かった為か、開花の時期が少し遅れているようだが、日隠林道が5月9日から10月頃まで工事の為通行止めとなるので、その前に五葉岳のアケボノツツジを見る事にした。
天気予報では晴れのち曇りと出ていたので、何とか花は見れるだろうと思っていたが、お化粧山あたりからガスがかかり始め、高度を上げるにつれ段々と視界が悪くなり、五葉岳山頂付近では視界は50メーター位まで落ちた。初めて登る五葉岳だったのでそこからの眺望や、アケボノツツジの咲き具合を楽しみにしていたが、何にも見えず残念だった。
 |
 |
 |
国道218号線を延岡方面へ走り、青雲橋手前から左下へ下ると県道6号へ出た。県道6号を宇目方面へ約14キロ程進むと赤川の中村橋が見えて来る。この橋を渡ると日隠林道の始まりで、林道の状況は橋を渡って1キロは舗装されていたがすぐに砂利道と変わった。この後林道は所どころ舗装された所もあったが、砂利道は凹凸がひどく根石で車底を擦らない様に、路面の状況に最大の注意を払いながら約30分程登ると、ゲート付近のお化粧山登山口に着いた。登山口には丁度8時に着いたが、既に福岡・大分・佐世保・鹿児島.宮崎・山口の他県ナンバーの車が道路脇に止めてあった。
今回の計画段階では、ゲートより2キロ先の大吹鉱山跡から登ろうと思っていたが、道路状況が極端に悪いのでこの2キロは走らない方が良いと言うアドバイスを得ていたので、今回はお化粧山登山口から登ることとし、私も道路幅が広くなっている所に駐車させ、早速準備に取りかかり8時15分に登山開始した。
 |
 |
 |
登山口はゲートの手前20メータ位の右側にあった。涸沢に沿って急坂の杉林を暫く進むと、涸沢と同じ高さとなる。この辺から山腹を登って行くと涸れた谷に変わり、辺にはヤマシャクヤクが見受けられたがまだ固い蕾みだった。暫く涸れた谷を息を弾ませながら登って行くと、正面に大きな岩が立ち塞がるので右へ回り込み、大きな尾根に上がった。
 |
 |
 |
下草の生えていない大きな尾根を暫く進むとアセビの花が咲く登山道に変わり、登り詰めた所にお化粧山の看板があった。この辺りからガスが出始めた。鞍部へ少し下り緩やかな尾根を登って行くと、ガイドブックに載っていたのと同じ格好をした、大きく枝を広げた大木が目に入って来たので、すぐに1571メーターピークのブナの三叉路に着いたのだなと分かった。ここから右へ行くと鹿納山で、左は大吹鉱山跡への下山道となっていた。
 |
 |
 |
ブナの三叉路から、緩やかな尾根を数回アップダウンを繰り返し進むと、じきにロープを設置した険しい岩場に着く、滑らない様にロープをしっかり握り締めながら登ると難なくお姫山に登り着いた。ガイドブックによると『山頂からは360度の展望を得られる素晴らしい展望所』と記載されているが今日は360度何にも見えない。残念!お姫山を反対側へ下り振り返ってみると、ガスに霞んだ山頂がぼおーっと見えるだけで何も良い所は無かった。山頂から岩場を下った所に乙女山への分岐点があり、右へ進むと乙女山、直進すると五葉岳で帰りに乙女山には登る事にした。
 |
 |
 |
お姫山から直進して鞍部へ向かい、最低鞍部へ達すると右方向へ瀬戸口谷へと下る登山道を確認しながら急坂を進むと、すぐに大吹鉱山跡登山口からの道が左から出合い、さらに急登で雨のためずるずる滑る道を用心しながら登ると五葉岳山頂に着いた。山頂はガスが立ち込み視界は50メートルくらいで期待したアケボノツツジにはこの山では出合う事も出来ず、また展望も利かず残念な登山となった。
 |
 |
 |
 |
 |
五葉岳をそこそこにして次の乙女山に向かった。往路で辿ったお姫山の岩場の手前から左へ下ると約15分程で乙女山に着いた。今回の登山の目的であるアケボノツツジに、意外にもこの山で出合い想定外だったので感激した。
乙女山山頂は、岩とヒメコマツと霧の中にぼおーと霞んで浮かび上がるアケボノツツジが醸し出す一級の墨絵そのもので、暫くの間ここで風情に浸り時を過ごした。
 |
 |
 |
登る計画に入れていなかった乙女山の想定外の風情を満喫して本格的に下山を開始した。当初下山は往路を辿る事にしていたが、ブナの三叉路で昼食休憩をした時、大吹鉱山跡登山口への下山を思いつき、どんなルートかを確認するために変更した。ブナの三叉路から右に少し下ると、すぐに道はほぼ一直線に急降下すると言う感じで、付近は下草の無いブナや楢の大木の生えた大斜面で素晴らしかった。1時間程下ると涸れた石ころの谷に出会ったので、涸沢の右側を下るとすぐヤマシャクヤクの群生が現れた。花はまだ蕾みが多く、咲いていたのは2~3株で満開にはもう少し時間が掛かりそうだ。この群生地から登山口はすぐの所だった。
 |
 |
 |
大吹鉱山跡登山口は事業所の施設があった事もあり、登山口には何十台も駐車出来る広いスペースがあった。ここから今朝登り始めたお化粧山登山口迄は約2キロであるが、林道の状態は聞いていた程悪くは無く、かえってゲートより下方が悪かったと思われた。
 |
 |
 |
||||
| アシビ | シロモジ | フウロケマン |
 |
||||||
| ヤマシャクヤク |
 |