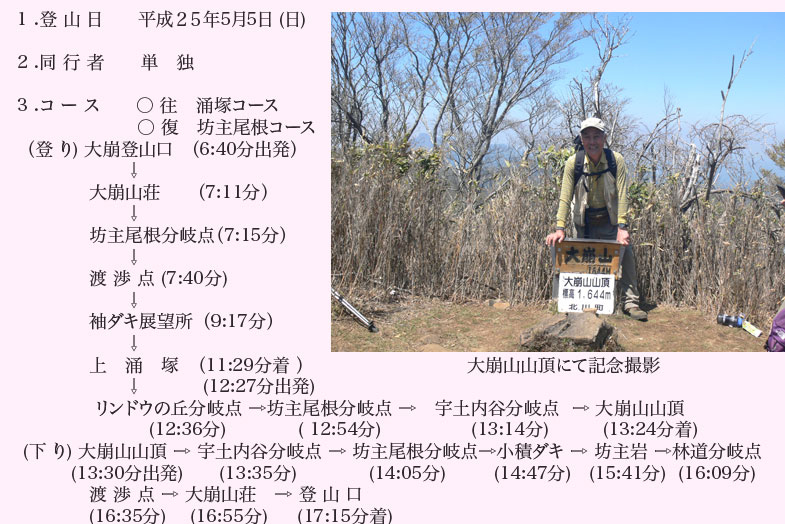坊主尾根のアケボノツツジは素晴らしかった
大崩山 1643.3m (二回目)
今年のアケボノツツジの開花は、例年より随分早くなりそうだと言う事で、先週4月28日親父岳から祖母山へ縦走を試みた。その時は4月中旬で既に黒金山尾根コースや宮原コースは開花したと言う事であり、それから約2週間経過しているので、丁度縦走路が見頃ではないかと思ったが、縦走路では全く咲いていなかった。そういう事もあって、今回は咲いていると言う情報のもと大崩山へ登った。登山口は祝子川渓谷の大崩山登山口に決め、駐車場所の確保のため登山口付近にテント前泊で望んだ。
 |
 |
|||
| 登山口付近の祝子川を大崩橋より眺める | 予想通り林道は車でいっぱい |
| 朝5時半に目覚め、朝食を済ませテントなどを方付け、6時半頃車を離れ登山口へと向かった。登山口は橋を渡り少し下った所で、林道には既に出発されたと思われる空の車がずらりと並んでいた。 |
 |
 |
|||
| 登 山 口 | 登山口付近の登山道 |
| 登山口の急坂を上ると道は比較的平坦になり、樫や椿等の生える常緑樹の中をルンルン気分で進んだ。この辺は大崩山へ向かう道とは思えない脚に優しい道で、もっと厳しい状況を想像していたので意外だった。この時期何処の山でもウグイスなど小鳥のさえずる声に朝の清々しさを感じるが、この道では全く小鳥のさえずる声は聞かれなかった。代わって渓谷の水の流れる音が、山の清々しさの中に静寂さを強調していた。 |
 |
 |
|||
| この道最初のハシゴとロープが現れた | 登山道界隈のミツバツツジ? |
| 登山道をルンルン気分で足早に進むと、登山口から20分程進んだ辺に最初の梯子や、ロープが設置された険しい場所を通過した。この辺には淡い藤色をしたミツバツツジ?が散見され、目を楽しませてくれた。 |
 |
 |
|||
| 大崩山荘 | 大崩山荘の内部 |
| 登山口の急坂を登り、沢を渡渉し梯子を登りながら脚を進めると、平坦な道になり30分程で大崩山荘に到着した。山荘付近の大木の下には、何張りもの色とりどりのテントが張られていたが、人影は見えなかった。20年位前の山荘は「幽霊屋敷」と言われていたらしいが、今は立派で明るい山荘だった。山荘の内部を覗いて見たが登山者やザック等は無く、ただ囲炉裏だけが中央部に居座っていた。 |
 |
 |
|||
| 三里河原方面と坊主尾根の分岐点 | しっかりロープを握りしめ滑らない様に進む |
| 山荘の一寸先にある標識に従い、三里河原方面へと脚を進める。梯子やロープを張った岩場を慎重に祝子川に沿って20分程進むと、三里河原方面と涌塚コースの分岐点に着いた。標識に従い左方向の涌塚コースへ進むとすぐ祝子川の渓流に出た。 |
 |
 |
|||
| 祝子川の渓流 | そびえ立つ小積ダキ |
| 薄暗い小道から祝子川の渓流へ出た途端パッと視界が開けた。「オー凄い」思わず声に出してしまう程、真正面に小積ダキが覆いかぶさる様にそびえ立っていた。感動の始まり。 |
 |
 |
|||
| 渡渉し岩を登り登山道へ入って行く | 岩屋と安全対策の小枝 |
| そびえ立つ小積ダキを眺めながら、ケルンを目印に渡渉して対岸に渡り、大きな岩を登り小積谷の登山道へ入って行った。 |
 |
 |
|||
| 小積谷の沢に沿って登って行く。 | 胸を突く様な急坂を登る |
| 小積谷の沢を幾つかの岩屋を見ながら、右に左へと沢に沿って登って行く。途中テーブル状の大きな岩から、右手へ進み急登するガレ場を梯子やロープに助けられながら、尾根道へと登って行く。 |
 |
 |
|||
| 袖ダキ手前の岩場に掛かる梯子 | 袖ダキ展望所から見た下涌塚の岩峰群 | |||
 |
 |
|||
| 乳房岩より涌塚の岩峰群を背景に記念撮影 | 袖ダキ展望所は多くの登山者で賑わっていた |
 |
 |
|||
| 袖ダキ辺のアケボノツツジ | 袖ダキ辺のアケボノツツジ |
| 尾根道に上がってからもさらに急坂が続き、尾根道が終わると袖ダキへの案内標識があった。その標識から左へ登るとロープが取り付けられた大きな岩の斜面が現れた。ロープをしっかり握り締め滑らないよう足元を確保しながら、全力でロープをたぐり寄せ這い上がると、そこは袖ダキ展望所で多くの登山者で賑わっていた。展望所に着き真っ先に目に飛び込んで来たのは下涌塚の岩峰群で、「おーすごい」の一言に尽きる。 |
 |
 |
|||
| 数えきれない程の梯子を登る | 下涌塚の岩峰から袖ダキを眺める |
| 展望所からの眺めを十分楽しみ、そのまま奥へ進み乳房岩にも立ち寄り、下涌塚の岩峰へ向かった。途中アルミの梯子を登り、花こう岩の感触を十分味わいながら、先ほど展望所から見上げた下涌塚の岩峰に40分程掛かり辿り着いた。 |
 |
 |
|||
| 岩窓より上涌塚の駒次郎ダキを覗く | 下涌塚から見た中涌塚の岩峰 |
 |
 |
|||
| 散り始めたアケボノツツジ | 散り始めたアケボノツツジ |
| 下涌塚や中涌塚の岩峰からの眺めを楽しんだ後、中涌塚からは一旦下って上涌塚の北側をまくようにして、設置された梯子やロープに助けられながら登り返し、上涌塚へ辿り着いた。この間アケボノツツジが見事に咲いていて、やや散り気味だったがそれでも素晴らしかった。この素晴らしさをカメラに収めたが、撮れた写真は目で見た程感動的には撮れなかった。 |
 |
 |
|||
| 上涌塚のアケボノツツジ | 上涌塚のアケボノツツジ |
| 登山口を出発してから上涌塚まで4時間50分を要し、11時29分に上涌塚へ着いた。上涌塚は丁度アケボノツツジが超満開で、あたり一面アケボノツツジに華やいでいた。体も随分疲れを感じたので、ここでアケボノツツジを見ながら1時間程ランチタイムを取る事にして、12時27分迄休憩した。 |
 |
 |
|||
| 坊主尾根分岐点から見た駒次郎ダキ | 坊主尾根分岐点 |
 |
 |
|||
| 縦走路のブナの大木 | 縦 走 路 |
 |
 |
|||
| 石塚辺のアケボノツツジは八部咲きだった | 大崩山山頂で記念撮影 |
| 上涌塚で1時間程休憩を取り最後の目的地大崩山山頂へと向かった。途中リンドウの丘からの出会い点や坊主尾根からの出会い点、続いてもちだ谷ルート、鹿川からの道が合流して石塚に着いた。山頂迄は石塚からは5分で、上涌塚を出発してから約1時間を要し、13時24分に大崩山山頂に到着した。山頂は多くの登山者で賑わっていたが、私が三脚を据え記念撮影を始めたところ、登山者がスーウと退かれてしまったので寂しい記念写真となった。一等三角点のある山頂は展望が良くないので、撮影を済ませすぐ石塚へ戻ったが、ここも登山者でいっぱいだった為、休憩は取らずそのまま下山を開始した。 |
 |
 |
|||
| 坊主尾根のアケボノツツジ | 小積ダギ入り口 |
| 下山は坊主尾根の分岐点まで戻り、右へ急坂を下りリンドウの丘を通って来た道と出会うと、ひたすら下りに徹する。左側に樹間から谷を隔てて見え隠れする、湧塚の豪快な岩壁の姿を見ながら下ると、次第にアケボノツツジが多くなり小積ダキの分岐点に着いた。左へ5分程で往復出来る山頂は意外にも思った程険しくなく足場も良かった。 |
 |
 |
|||
| 小積ダギから上涌塚方面を見る | 小積ダギから像岩を見下ろす |
| 小積ダギは今朝方祝子川を渡渉しながら見上げ最初に大感動を受けた岩峰だ。その岩峰から今は見下ろしていると云う新たな感動を覚えた。 |
 |
 |
|||
| 像岩下のトラバース | 坊主尾根の主「坊主岩」 |
| 小積ダギを後にし分岐点を左に下り、広い岩壁を滑らない様に用心深くロープで下ると、今度は切れ落ちた像岩下のトラバースを、渡されたワイヤーロープにすがって慎重に進んだ。ここより下は梯子やロープ場の連続で坊主尾根コースで一番の悪場だ。岩壁の下や岩壁の間を通り坊主岩から右方向へ進み、ほとんど垂直に感じられる崖をひたすら下って、樹林帯の急坂をくだると林道分岐点に着いた。 |
 |
 |
|||
| 林道分岐点の標識 | 最後の渡渉点 |
| 崖の様な登山道をやっとの思いで下り、林道分岐点まで辿り着いた時はホットした。後は下小積谷を川に沿って下り、祝子川本流に出合った所で最後の渡渉をした。大崩山荘は渡渉点からすぐの所で行きに見かけたテントは二張りに減っていた。後は往路をひたすら引き返し、登山口に17時15分に帰り着いた。 |
 |